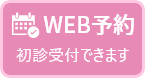よくみられる主な疾患
尿漏れ

尿漏れとは、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態のことをいいます。特に中高年の女性に多くみられ、年齢とともに増えていく症状です。実際には多くの方が悩んでいますが、「恥ずかしい」「年のせいだから」と受診をためらう方も少なくありません。しかし、尿漏れは原因を正しく見極めることで改善できる症状です。
当院では、患者さま一人ひとりの状態に合わせて適切な治療を行っています。恥ずかしがらずに、まずはご相談ください。
尿漏れの主なタイプ
尿漏れにはいくつかのタイプがありますが、代表的なものは「腹圧性尿失禁」と「切迫性尿失禁」です。
腹圧性尿失禁
咳やくしゃみ、笑ったとき、重い荷物を持ったときなど、瞬間的にお腹に力(腹圧)がかかったときに尿が漏れてしまうタイプです。
骨盤底筋(こつばんていきん)と呼ばれる筋肉が弱くなり、尿道をしっかり締める力が低下することが原因です。出産や加齢などで起こりやすく、骨盤底筋トレーニングや薬による治療で改善が期待できます。
切迫性尿失禁
「急に強い尿意を感じて我慢できずに漏れてしまう」というタイプです。脳や膀胱の排尿コントロールがうまくいかず、膀胱が勝手に収縮してしまうことが原因と考えられています。
トイレが間に合わず漏れてしまうことも多く、外出時や仕事中など日常生活に支障をきたす場合があります。薬物療法などで症状を和らげることが可能です。
当院の治療方針
当院では、問診や検査によって尿漏れのタイプと原因を明確にし、
- 骨盤底筋トレーニング
- 薬物療法
など、患者さまの症状に合わせた治療を行っています。
「少し漏れるだけ」「たまに起こる」など、どんな小さな悩みでも構いません。お気軽にご相談ください。
過活動膀胱
過活動膀胱は、自分の意思とは関係なく膀胱の筋肉(排尿筋)が勝手に収縮してしまうことで、急に強い尿意を感じる・トイレが間に合わないなどの症状が出る病気です。
「急にトイレに行きたくなる」「夜何度もトイレに起きる」「我慢できずに漏れてしまう」などの症状がある方は、過活動膀胱の可能性があります。
この病気は、加齢やホルモン変化、脳・神経の働きの乱れ、ストレスなどが関係しているといわれており、特に中高年の男女に多くみられます。
主な症状
- 急に強い尿意を感じる(尿意切迫感)
- トイレが近い(頻尿)
- トイレが間に合わず漏れてしまう(切迫性尿失禁)
- 夜中に何度もトイレに起きる(夜間頻尿)
治療について
過活動膀胱は、治療によって改善が期待できる病気です。当院では、症状の程度や原因をしっかりと見極めたうえで、以下のような治療を行っています。
生活習慣の改善指導
水分摂取の調整や、カフェイン・アルコールの制限、骨盤底筋トレーニングなどを行います。
薬物療法
膀胱の過剰な収縮を抑えるお薬(抗コリン薬やβ3刺激薬)を用いて、尿意や頻尿の症状を改善します。
ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法(保険適用)
内服治療で効果が不十分な方には、「ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法」を行っています。
この治療は、膀胱の筋肉にボツリヌス毒素を注入して過剰な収縮を抑え、尿意を落ち着かせる方法です。効果はおよそ6〜9か月持続し、繰り返し治療を行うことも可能です。
早めの受診をおすすめします
「歳のせいだから仕方ない」「恥ずかしくて相談しづらい」と感じる方も多いですが、過活動膀胱は治療で改善が期待できる疾患です。
少しでも気になる症状がある場合は、お早めにご相談ください。
神経因性膀胱
神経因性膀胱とは、排尿をコントロールする神経(脳・脊髄・末梢神経)に障害が起こることで、尿をうまくためたり出したりできなくなる病気です。
排尿の仕組みは、脳からの指令が脊髄や末梢神経を通じて膀胱に伝わることで成り立っています。その経路のどこかに障害が生じると、尿がたまりにくい・出にくい・漏れてしまうなど、さまざまな排尿障害が起こります。
神経因性膀胱のタイプ
神経因性膀胱は、障害の部位や性質によって主に2つのタイプに分けられます。
痙性神経因性膀胱(けいせいしんけいいんせいぼうこう)
脳や脊髄など、仙髄より上位の中枢神経に障害が起こった場合にみられるタイプです。神経が過敏になり、膀胱が勝手に収縮してしまうため、尿を十分にためられず、頻尿や尿漏れが起こりやすくなります。
主な原因として、
- 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血
- 脳腫瘍
- 多発性硬化症
- 脊髄損傷(不全損傷を含む)
などがあります。
これらは早期発見・治療が重要な疾患も多く、気になる症状がある場合は早めの受診をおすすめします。
弛緩性神経因性膀胱(しかんせいしんけいいんせいぼうこう)
膀胱へつながる末梢神経の障害によって起こるタイプです。
膀胱の筋肉が弛緩してしまい、尿をうまく押し出すことができなくなります。尿がたまっても尿意を感じにくく、排尿困難や尿が出きらない、逆に溢れて漏れてしまうといった症状がみられます。
主な原因として、
- 脊椎損傷や脊髄疾患
- 先天性疾患(脊髄髄膜瘤など)
- 骨盤内臓器(子宮・直腸など)の手術後の神経障害
などがあげられます。
治療について
神経因性膀胱の治療は、原因疾患の治療に加え、膀胱機能を維持・改善し、腎臓への負担を防ぐことが目的です。
当院では、以下のような方法を症状に応じて行います。
- 薬物療法(膀胱の収縮を抑える・排尿を助ける薬)
- 間欠的自己導尿(尿が出にくい方への指導)
- ボツリヌス毒素膀胱注入療法(過活動型の場合)
- 原因疾患に対する他科連携治療
神経因性膀胱は放置すると腎機能低下につながるおそれもあります。「尿が出にくい」「出ても残っている感じがする」「夜何度もトイレに行く」など、気になる症状がある場合は早めにご相談ください。
膀胱炎
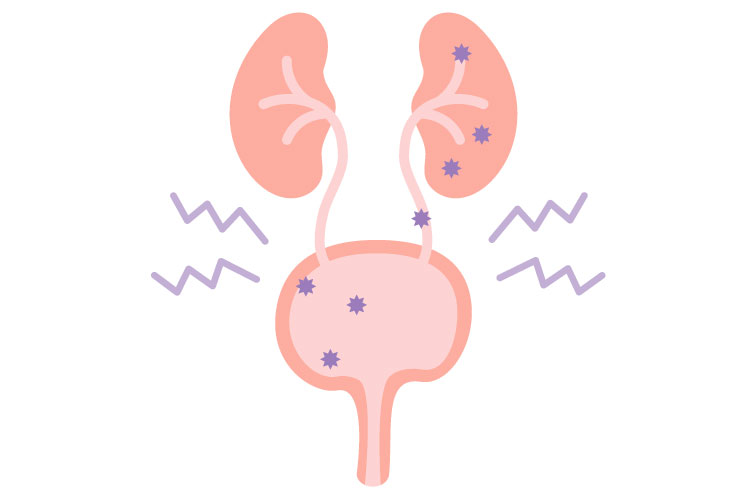
膀胱炎は、その名のとおり膀胱に炎症が起こる病気です。特に女性に多くみられる疾患で、人生のうち一度は経験する方も少なくありません。
女性は男性に比べて尿道が短く、肛門や膣など外陰部から膀胱までの距離が近いため、細菌が侵入しやすい構造になっています。このため、疲労やストレス、冷え、風邪をこじらせたときなどに免疫力が低下すると、膀胱内で細菌が増えて炎症を起こしやすくなります。
主な原因
膀胱炎の多くは、大腸菌などの細菌が尿道から膀胱内に侵入し、増殖することで発症します。以下のような状況がきっかけとなることがあります。
- ストレスや疲労の蓄積
- 冷えや免疫力の低下
- 水分摂取が少ない
- 性行為後の不衛生な状態
- 排尿を我慢する習慣
主な症状
- 排尿時の痛みや違和感
- 頻尿(何度もトイレに行きたくなる)
- 残尿感(出し切れない感じ)
- 下腹部の不快感・痛み
- 尿のにごりや強い臭い
症状が進行すると、血尿が出る場合もあります。
治療について
膀胱炎は多くの場合、抗菌薬(抗生物質)の内服で数日〜1週間ほどで改善します。
治療中は以下の点に注意が必要です。
- 水分をしっかり摂る(細菌を洗い流す)
- 排尿を我慢しない
- 下半身を冷やさない
- アルコール・刺激物を控える
症状が繰り返す場合や、発熱・背中の痛みがある場合は、腎盂腎炎など上部尿路感染症の可能性もあるため、早めの受診が大切です。
当院での対応
当院では、尿検査や超音波検査を行い、膀胱炎の重症度や再発の原因を丁寧に評価します。再発を繰り返す方には、生活指導・予防策・基礎疾患のチェックを含めた総合的な治療を行っています。「痛い」「何度もなる」とお悩みの方は、我慢せずご相談ください。
腎盂腎炎

腎盂腎炎は、腎臓の内部(腎盂・腎実質)に細菌が感染して炎症を起こす病気です。
多くの場合、膀胱炎など下部尿路の感染から細菌が尿の通り道を逆行し、腎臓まで到達して発症します。原因菌の多くは大腸菌で、女性に多くみられる傾向があります。
主な症状
膀胱炎よりも症状が強く、全身の異常をともなうのが特徴です。
- 背中や腰の痛み(腎臓のあたり)
- 38℃以上の発熱や悪寒
- 吐き気・嘔吐・倦怠感
- 頻尿・排尿時の痛み
- 尿の濁りや血尿
これらの症状がみられる場合は、膀胱炎が腎臓まで進行している可能性があり、早急な受診が必要です。
治療について
腎盂腎炎は放置すると、細菌が血液中に広がり敗血症(命に関わる重篤な感染症)を引き起こすおそれがあります。そのため、医師の診断のもとで適切な抗菌薬治療を行うことが重要です。
軽症の場合
内服薬による治療を行い、十分な水分摂取・安静を保ちながら経過をみます。
中等症〜重症の場合
発熱や全身症状が強い場合は、点滴による抗菌薬治療や入院が必要になることもあります。
再発予防のために
- 水分をこまめにとる
- 排尿を我慢しない
- 下半身を冷やさない
- 性行為後は早めに排尿・洗浄する
- 膀胱炎を繰り返す場合は早めに検査・治療を
腎盂腎炎は適切な治療で改善しますが、再発や慢性化を防ぐことが大切です。「熱が下がらない」「腰が痛い」「膀胱炎が治らない」と感じたら、早めにご相談ください。